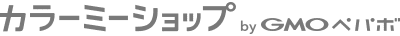夢産地とさやま開発公社の『無農薬柚子の育て方』をご紹介
『無農薬柚子の育て方』目次
接ぎ木で作る柚子の苗
ゆず苗が出来るまでの接ぎ木の作業の様子を紹介します。接ぎ木とは、少しだけ切った枝と幹をくっつけると、ひとつの植物のように成長しはじめるという植物の神秘。
メリットとしては、連作障害を受けにくくなる、実がなるまでの年数を短縮できる、などが挙げられます。接ぎ木は、9月の天気の良い日に行われました。
キコク(カラタチの木)の台木に、ゆずの穂木(挿し木や接ぎ木に使う枝)を接ぎ木します。こちらでは穂木をキコクに接ぎ木をする作業を、工程に分けてご紹介します。
- まず、ゆず園から穂木を採ってきます。
- 1つの穂木から芽の部分だけを切る。切り口はまっすぐに。


- ナイフを入れて切こみをつくる

- 切り込みをつくったところに穂木を、ぴたっとハマるように差し込んでいく。

- 最後にメデールというテープでクルクルまきます。

- 接ぎ木完了です。ここから芽がでて大きくなります。

- 農家の方にも手伝ってもらい3,000本接ぎ木しました。

- ここ土佐山ではもうすぐ柚子の収穫の時期を迎えます!
地域が柚子の香りに包まれる、いそがしくも美しい冬のはじまりです。
=== その後 ===
柚子接ぎ木の成長
いま畑では、来年の4月出荷用のゆず苗を作っています。接ぎ木したものが、しっかりキコクの苗についていて大きくなってきました!接いだばかりの時はこんな様子だったのが…、右側にくっついている緑色の物体が接いだゆずの芽です。約10ヶ月ほどでこんなに成長。接ぎ木成功!


上の写真は9月に接ぎ木したものですが、「春接ぎ」といって同じ作業を5月にも行います。そちらはまだこんな感じ。すこしずつ、緑色の芽が出てきています。芽が出てくれば接ぎ木成功です。

これからは害虫駆除に追われます。アゲハやカミキリ虫は天敵で、葉っぱを食べられたりして大変!来年春の出荷に向け、気の抜けない日々がつづきます。苗ではなく、成木のほうは花が咲き終ったところです。

満開の時はすごくいい香りにつつまれていました。花が終わったところからは、小さな実がのぞいているのもあります。ゆずも、収穫の11月まで草刈りなど手入れがつづきます。
=== その後 ===
柚子の苗の出荷
土佐山ジンジャーエールにも利用されている、土佐山の特産品である無農薬柚子。新緑の季節、ここ高知県の山間では、先日ゆず苗の出荷作業が行われました。ゆずはまず、キコク(カラタチの木)の台木にゆずの穂木(ほぎ)を接ぎ木します。1年かけて下の写真くらいの大きさになり、今回はこちらを出荷しました。
まずは、スコップで慎重に苗を掘りおこします。

良い苗、悪い苗を選別し、10本ずつ束にします。おけの水にたっぷりと付け、それを今度は米の袋でまいて出荷準備完了です。


一日半で、2500本ぐらい準備できました。ゆずには長いトゲがあり、苗の時から収穫まで、このトゲには苦労させられるのです…。これから立派な柚子が実るまでの様子を、レポートしていきたいと思います!
=== その後 ===
無農薬柚子の収穫
パチンとハサミが鳴って、添えた手にユズの重みがかかる。ズシリとした実から、あのユズ独特の青く、酸っぱく、かぐわしいにおいが香ってくる。周りを見渡すと一面に黄色。ユズ、ユズ、ユズ…。ユズのシーズンが始まりました。これからしばらくはユズの収穫に明け暮れることでしょう。
ここ高知県土佐山のユズ加工場では、ユズの受け入れが始まり、あたりいちめん香りが立ち込めています。とさやま開発公社でもユズの果汁やスイーツを作るために、ユズの収穫をはじめました。そして今回は、土佐山アカデミーの方々にも収穫のお手伝いをしていただきました。

痛い、痛い、と言いながらトゲだらけのユズの木の中に入って行って、ユズをカゴいっぱいに採っていました。そこでゆさゆさと揺れるものだから、トゲにユズや葉っぱが擦れて、その周辺はひときわ香りがたってましたね。
畑は谷間にありますが、南側の傾斜地で日当たりもよく、11月とはとても思えない陽気でした。トゲ対策のために厚着をしていて服の下は大汗でしたが、ユズの黄色がもうすぐやってくる冬の訪れを感じさせ、何とかこらえられたかな?という感じです。

今冬は特に冷え込むそうです。皆さん、冬至の日はユズをお風呂に入れて、「ユズ湯」で暖まりませんか?あとユズを横半分に切って、中身をくりぬいて、それをお猪口にして日本酒を飲むと、とっても美味しいらしいですよ。要注意w
土佐山の無農薬柚子で作られた商品のご紹介
土佐山で作られた無農薬柚子をもとに、様々な商品を開発しています。どれも味に自信がある商品ばかりですので、是非お試しください。
土佐山の有機生姜を、これからもよろしくお願い致します。
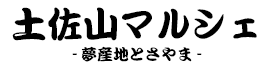
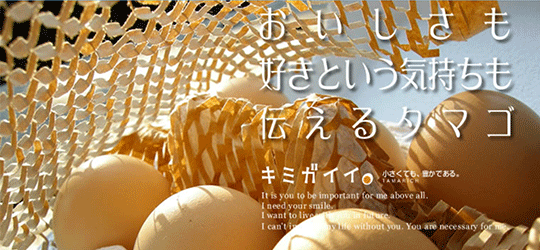

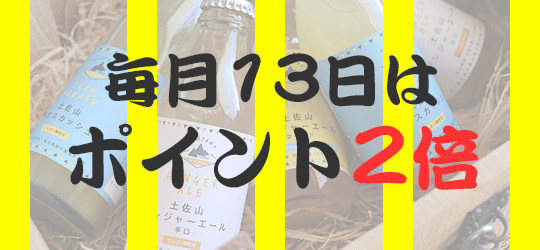





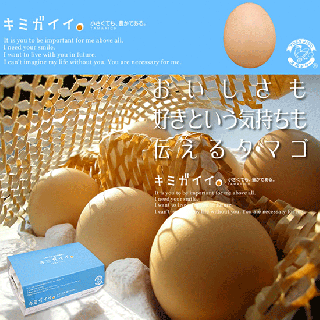
![土佐山ジンジャーエール [ 02 Mild ]](https://img07.shop-pro.jp/PA01415/347/product/130782865_th.png?cmsp_timestamp=20180425183701)
![土佐山 新ジンジャーエール辛口 柚子スカッシュ MIX Mサイズ [ TOSAYAMA YUMESANCHI ]](https://img07.shop-pro.jp/PA01415/347/product/156130977_th.jpg?cmsp_timestamp=20201210122119)
![土佐山果実 山育ち柚子果汁 塩なし [ TOSAYAMA YUMESANCHI ]](https://img07.shop-pro.jp/PA01415/347/product/130863210_th.png?cmsp_timestamp=20181208123304)

![土佐山ジンジャーエール 辛口 [ 01 Premium mini 200ml ]](https://img07.shop-pro.jp/PA01415/347/product/132625445_th.png?cmsp_timestamp=20180621150548)